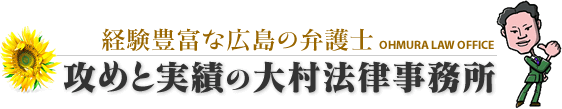相続分の原則は、被相続人との関係で決められていますが、変更される場合があります。それが、特別寄与料と特別受益です。
特別寄与料
推定相続人が全員、均等に被相続人と関わりを持っているということはありえません。
特定の人がもっぱら生前の被相続人の世話をしていたケースも多いでしょう。
とはいえ、民法では、親族間には扶養の義務があります。
原則として無償で面倒を見るべきということです。
したがって、このような場合でも、当然に相続分が多くなるわけではありません。
ただ、被相続人の財産の維持、増加に功績がある場合には、一定のお金を支払うことが認められました。
これを「特別寄与料」といいます。
2019年の7月までは、『寄与分』という名前で、相続分の上乗せが認められていましたが、相続人にしか認められませんでした。
相続人にしか相続分はありませんから、制度的な限界として、相続人以外には認めようがなかったわけです。
とはいえ、誰でもOKというのでは際限がなくなってしまいますので、親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の親族)という限定は残りました。
これにより、息子がいるが折り合いが悪く甥に寄与が認められる場合には、特別寄与料を支払うことが認められることになったわけです。
特別寄与料は、まずは相続人に対して請求し、協議して決定することになっており、協議がまとまらない場合には裁判所に協議に変わる処分を求めることが出来ます。
典型的な例としては、相続人が被相続人に対し財産を拠出したとか、家業に無償で従事した結果、被相続人の生前の財産が増えた(あるいは減少を免れた)というような場合が挙げられます。
では、特定の親族が被相続人の身の回りの世話をしたというだけような場合はどうなるでしょうか。
現実に主張される場合の大半なのですが、これは本来、制度が想定する典型的なケースではありません。
とはいえ、そのおかげで、介護のための付添いの費用がかからなかったという意味で、財産の維持・増加があったと考えることもできなくはありません。
ただ、私の経験では、裁判所がこのような形の寄与分を認めることは稀です。
おそらく、「扶養は無償」という原則があるということ、実際に無償で介護せざるを得ない財産の少ない親族も多数いること、財産の維持増加の有無だけでなく程度まで判断をするのは難しく、裁判官の腰が引けてしまうことなどが原因でしょう(とはいえ、統計上は皆無ではありませんので、裁判官によっては広く認める人がいるのかもしれません)。
しかし一方で、、本当に頑張った親族にそれなりの褒賞を与えるのは、一般常識としては自然ではないでしょうか。
その意味では、裁判所の判断に固執せず協議により寄与分を認めることはむしろ、親族間の助け合いの精神にかなうものだと思いますから、一律に否定されるべきものでもないでしょう。
なお、裕福な家庭の場合、扶養している人に対しては、一定の扶養料を渡していたり、ことあるごとにお小遣いやプレゼントを渡しているケースも少なくありません。
言ってみれば生前に寄与分に相当する給付をしていることになりますが、裁判所はこのようなケースについては、寛容に追認するケースが多いように思います。
その意味では、被相続人は、自分が生きている間に、ある程度感謝の気持ちを形にしておいたほうが良いのかもしれません。
ただ一方で、やりすぎると後述の特別受益の問題が生じますので,その点にも注意が必要です。
なお、以上は、基本的には寄与分の時代の話で、特別寄与料に改正されてからはどうなるか分からない部分があります。
とはいえ、立法者意見では、寄与分の時代と、求められる貢献の程度は変わらないといわれているので、今後もあまり変わらないかもしれません。
一方で、今回の改正法では、若干条文が変わっています。
「療養監護その他の労務の提供」と、療養監護のみが労務提供の典型的な場合であると唯一例示される形になったのです。
寄与分でも療養監護は例示されていたのですが、その前に事業に関する労務提供財産上の給付も例示されており、どちらかというと純粋に財産が増えたことに着目する制度と理解されていました。
事業に関する労務提供が例示から削除されたことで、もしかしたら、特別寄与料は寄与分の時代よりは多少なりとも柔軟に認められるようになるかもしれません。
特別受益
被相続人が推定相続人に対し、例えばマイホームの建築資金を援助したとか、結婚に際して引越し代や新婚旅行の費用などを援助したなど、特定の推定相続人に多くの財産を渡すケースは多いでしょう。
家族としての普通の営みと思いますが、一方で、受け取った人が相続人の一部に限られているような場合、相続に際してこれらの事情を全く無視すると、不公平でしょう。
そこで民法では、婚姻や養子縁組のため、あるいは遺贈や生計の資本として贈与を受けた場合には、その分も遺産と合算して総額を計算し、それに相続分を乗じて個々の取り分を計算した上で、贈与を受けた人については贈与分を控除する(事前に受け取ったものとして扱う)ことになります。
例えば、子どもAB2人が相続人のケースを考えてみましょう(配偶者は先に死去)。
Aには結婚の際200万円を贈与し、一方Bにはマイホーム建築資金として600万円を援助していた父親が、2000万円の財産を残して亡くなったとします。
この場合、総額が 200万円+600万円+2000万円=2800万円となり、ABそれぞれ1400万円が取り分ということになります。
そして、Aは200万円、Bは600万円すでにもらっているので、遺産の2000万円は、
Aが 1400万円-200万円=1200万円
Bが 1400万円-600万円=800万円
受け取ることになります。
実際の紛争
実際の紛争でも、いくら貰えるかは当事者の関心事です。当然、これらの論点が問題になるケースも少なくありません。
しかし、いずれも、長い親族関係の中で生じる事情によって認定されます。
詳しい事情がわからないケースも多いです。
感情的対立が比較的少ない場合には、話し合いで認められるケースもありますが、対立が大きい場合では、相手の言い分には一切耳を貸さないというケースもあります。
どこまで争うべきか、争うためには何が必要か、といったことを見極めるためには、弁護士のサポートは不可欠だと思います。
相続問題で弁護士をお探しの方へ
大村法律事務所は依頼者の正当な利益を守るために、攻めの姿勢で、できる限りの手段をつくし弁護いたします。
相続問題は、広島で25年以上の実績、地域密着の大村法律事務所にお任せください。